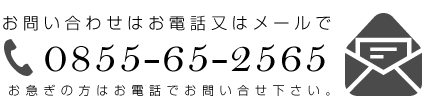小林:
久城社中所有の木彫り面数点と社中独自の演目「双剣の舞」が、貴重な文化財として益田市の指定を受けておられますが、これらは、どなたが、いつ頃に作られて、今日まで伝えられているのかお聞かせください。
岡戸座長:
久城社中が所有している面のうち、益田市の文化財に指定されている面は、7つありますが、作者は全て不明なんです。「鬼返し」の面でいうと、もともと満州の方からきたとか、それを大阪の商人が売りに来たのを米何升かと交換したなど、諸説いろいろあるようです。
私が子どもの頃、社中で舞っていた団のおじさんから聞いた話ですので、おそらく明治の初期ぐらいの出来事ではないかと思います。
久城社中自体も江戸末期が発祥ですが、今の形態になったのは明治時代に入ってからですので、大体そのくらいの時代に面も揃ってきたんじゃないかと推測されます。
小林:
鬼返しの面は資料で見ると、アジアの方から来た面ではないか、と書かれていましたから、満州から来たというのは現実味がありますね。
現在、その面は使われていますか。
岡戸座長:
今は痛みが酷いのでレプリカ品を使っています。大会では文化財の面を使っています。
指定の文化財を受けている7つの面のうち、実際に舞台で使っている面は「鬼返し」以外は全て使っています。
小林:
今回、私は「石見野」で登場する『柿本人麻呂』の面を作らせていただきましたが、もともとこの面は「天神」の『菅原道真』でも使われている神面ですが、他の「切目」や「大江山」の『源頼光』にも使われていますね。
神田さん:
はい。
ただ、使用する率が高く、同じ面が出てくると続けて舞えなくなります。
岡戸座長:
それぞれの舞で、舞いなりに応じた面の表情となり、同じ面ではあるが、それぞれ違った味が出ているのではないかと思います。
小林:
面を作る者からみれば、一つの面で「頼光」になり「切目王子」にもなり、「人麻呂」の面にもなるということは、それだけ表情豊かな万能な面だといえます。
かたや表情が決まった面は、その役どころにしか使えないっていう逆に難しい部分もあると思います。そういう面でいうと、久城社中の面はとても色んな表情を出してくれるなあと僕は思っています。仏さんのような表情もあり、ちょっと人間離れしたような顔もあるんだけど、でもよく見ると笑ってるような感じもする。
とても興味深い面です。
舞う側としては、注意している点などがあるのでしょうか。例えばこの演目では顔を上げ気味に舞うとか。
山本さん:
一つは「頭(ず)」の切り方ですね。この舞ではゆっくりするとか。
神田さん:
それぞれ舞の所作が違うので、その所作を作れば、面の表情もそれに応じてきます。面は後付けじゃないけども、舞に応じて自然とその面の良さが出て来る、そういうイメージなんですよね。
石見神楽とは
神楽団インタビュー
石見神楽保存会久城社中
「久城伝統の舞を受け継ぐ!」石見神楽保存会久城社中
- 団体拠点
- 島根県益田市久城町櫛代賀姫神社内
- 団体設立期
- 江戸末期から
- 練習日
- 毎週月曜日
- 団員数
- 30名(平成24年3月現在)
- インタビュアー
- 小林泰三
- 参加者
- 岡戸顕栄氏(座長)、山本勝一氏、神田惟佑氏